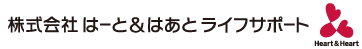こんにちは!はーと&はあとの松本千奈美です(*^▽^*)
先週、スチームコンベクションオーブンの勉強会に行ってきました。
スチームコンベクションオーブンとは、名前の通りスチーム(水蒸気)と熱風を利用したオーブンで「煮る」「焼く」「蒸す」と様々な調理ができます。また、スチームを利用して焼くことで焼き魚などをしっとりと仕上げることができたり、調理時間を短縮することができます。
大量調理では、作る人によって味が変わらず常に均一であることも重要ですが、スチームコンベクションオーブンを使うことによって、業務を標準化することができ誰が作っても同じ仕上がりにすることができるのもメリットです。
「はあとバランス」や「おいしゅ」の製造においても、スチームコンベクションオーブンは欠かせません。
様々な機能がついていてとっても便利な機器ですが、その分使いこなすのも大変です!まだまだ私自身、知らない知識や方法がたくさんあり定期的に勉強会に参加し調理方法やスチコンの使い方などを勉強しています。
勉強会に参加することで、「こんなメニューも出来そうかな?」とアイデアの幅が広がります。スチームの量や焼き時間、温度を少し変えるだけでも出来上がりが全然違うものになります。実際にデモンストレーションで調理されたものを食べ比べてみても違いがわかり面白かったです。
ちなみに・・・はーと&はあとのデイサービスでは、スチームコンベクションオーブンを使って焼き立てパンを焼いています!ご利用者様からも好評です★
今週は、東京で製造に関する研修に参加してきます!!研修で学んだことを「はあとバランス」や「おいしゅ」の商品開発に役立てて、よりよい商品にしていけるよう勉強していきたいです。

写真は、全然関係ないですが・・・(パンの写真を載せたかったのになかったです・・・(^_^;))今週誕生日なので家族にお祝いしてもらったときの写真です★美味しいものを食べて幸せな時間でした!ついに20代ラストになってしまいます・・・!!仕事もプライベートも全力で楽しんで充実した1年になるように頑張ります!★
皆様こんにちは!! 管理栄養士の篠原大之です。寒い日が続いていますが、体調など崩されていないでしょうか?さて、体調を崩しやすいこの時期。テレビCM、スーパーで、乳酸菌飲料の宣伝がよく目に留まります。そこで、今回は乳酸菌の効果についてお話させていただきます。乳酸菌と言えば、ヨーグルト、チーズなどを思い浮かべるかと思いますが、この乳酸菌は主に2種類に分類することができます。それは、動物性乳酸菌と植物性乳酸菌です。
動物性乳酸菌:ヨーグルト、チーズなど。はあとバランスでは、「鮭のトマトチーズ焼き」「ホキのグラタン」にチーズが使用されています。
植物性乳酸菌は、漬物類、大豆が原料の味噌や醤油など。はあとバランスでは、「サバの味噌煮」「ナスの田楽」に味噌が使用されています。
乳酸菌の効果について
◎風邪予防
乳酸菌は、腸管機能を活性化させ、病気などから体を守る効果があります。
私たちの体は加齢とともに悪玉菌が増えてしまう傾向がありますが、腸内の細菌バランスを整えてくれるので、つらい便秘や困った下痢の改善にも繋がります。
◎オススメの摂取方法:乳酸菌は胃酸に弱いです。そのため、空腹時以外に摂取することをオススメします。
これら乳酸菌は、一度摂取しただけでは効果がなく長期的に継続する事で効果が得られます。ちなみに私も味噌汁、ヨーグルトは基本的に毎日摂取しています。また、様々販売されているヨーグルトですが、自身に合うヨーグルトがあります。私はそれを見つけるために2週間同じヨーグルトを食べ、合わなければ別のものを試したりしました。是非皆様も乳酸菌を継続的に摂取していただき、健康な体で過ごしましょう!!

先日、京都のおばんざい屋で食べた大根の味噌田楽!!ここにも味噌が・・・
美味しかったです!!
お問い合わせ
0120-919-257(通話無料)
はーと&はあと 管理栄養士 篠原大之
皆様!こんにちは(*^▽^*)
管理栄養士の松本千奈美です。本年もよろしくお願いいたします。
1月になり、ますます寒さも厳しくなりました。インフルエンザや風邪も流行しています。予防にはこまめな手洗いやうがいが大切ですが、バランスの良い食事をとることも重要です。そこで、今月は風邪予防のポイントをお話ししたいと思います。予防に効果的な主な栄養素は、タンパク質・ビタミンA・ビタミンCです。
<タンパク質>魚や肉、大豆製品(豆腐・厚揚げ・納豆)、乳製品などに多く含まれます。体を作る元となる栄養素で体の中で常に作り替えられています。タンパク質の中には体で合成されないものもあるため、食事から摂取する必要があります。また、免疫力に関わるタンパク質もあり、不足すると風邪にかかりやすくなります。
<ビタミンA>鼻や喉の粘膜を強化し、菌の侵入を防いでくれます。人参・かぼちゃ・ホウレン草 などの緑黄色野菜に多く含まれます。脂溶性ビタミンと呼ばれ、油と一緒にとることで吸収率がアップします。冬場は乾燥しやすいため、適度に脂質をとることも風邪 予防に有効です。
<ビタミンC>いちごやみかんなどのフルーツ、キャベツ・大根などの淡色野菜、芋類に多く含まれています。風邪の予防や回復を早めてくれる役割があります。
ちなみに・・・菌やウイルスは熱に弱いため、体の中から温め体を冷やさないようにしましょう。体を温めてくれる食材には生姜や玉ねぎ、ニラ、肉類、鮭などがあります。
風邪予防におすすめのはあとバランスメニューは、『鮭のトマトチーズ焼き』『鯖の生姜煮』『人参の肉みそ炒め』などです♪♪
今回は、ご家庭でも作っていただける人参の肉みそ炒めのレシピをご紹介します★



新年明けましておめでとうございます。管理栄養士の篠原大之です。
2020年は、東京オリンピックの年!!日本中が全世界から注目される年になるかと思われます。全世界は難しいかと思われますが、ちなみにの話から気になる情報をどんどん発信していけたらなと思っております。本年度もよろしくお願いいたします。
さて、今回は1月7日と言えば...そう!! 七草がゆの日です。セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ。小学生の頃、先生に暗記するようにと言われ必死に覚えた記憶があります。七草がゆを食べる習慣は江戸時代に広まったと言われています。では、なぜ七草がゆを食べるようになったのでしょうか?七草は、早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われました。七草がゆが定着した背景には、お正月のご馳走に疲れた胃腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬場の栄養補給をする効用もあり、この日に七草がゆを食べることで、新年の無病息災を願うようになりました。それぞれに意味や効能があります。
芹(せり) 芹には、「勝負に競り勝つ」という意味合いが込められています。胃を丈夫にする効果や、解熱効果、利尿作用、整腸作用、食欲増進などの効果があると言われています。
薺(なずな) 薺には、「なでることで汚れを取り除く」という意味合いが込められています。解毒作用や利尿作用、胃腸障害やむくみに効果があると言われています。
御形(ごぎょう) 御形は、仏の体をあらわしており、咳や痰、のどの痛みに効果があると言われています。
繁縷(はこべら) 繁縷は、「繁栄がはびこる」という意味合いが込められています。胃炎や歯槽膿漏に効果があると言われています。
仏の座(ほとけのざ) 仏の座は、仏の安座という意味合いが込められています。胃の健康を促し、食欲増進の効果があると言われています。
菘(すずな) 菘は、神を呼ぶ鈴という意味合いが込められています。胃腸を整え、消化を促す効果があると言われています。
蘿蔔(すずしろ) 蘿蔔は、汚れのない清白という意味合いが込められています。風邪予防に効果があると言われています。
毎年、スーパーで七草がゆセットが販売されています。七草がゆを食べてこの1年を元気に過ごしましょう!!

先日、平安神宮へ初詣に行って参りました。皆様にとってこの一年が素晴らしい年になりますように!!