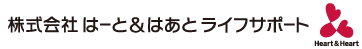こんにちは!管理栄養士の松本千奈美です。
12月に新発売したおいしゅですが、春に向けリニューアル致しました!!
販売開始以降、たくさんの反響を頂きました。実際に試食していただきそこで現場で働かれている方の声をたくさんいただきました。今回のリニューアルはそれを踏まえ12月よりさらにパワーアップしました。よりおいしく、彩りよくそして栄養価を統一することにより献立に組み込みやすくしていただけるよう工夫しました。
わたしが、おいしゅの開発でこだわった点の1つに「実際の現場で使いやすいこと」というのがあります。どんなに美味しくても、栄養バランスがよくても、忙しい現場で誰にでも簡単で使いやすい商品でなければ意味がないと思ったからです。
おいしゅは、1つの容器に3種類のおかずが入っています。忙しく人手不足の厨房で朝食に3品作り、さらに盛り付けるのはとても大変です。朝食準備には、おかずの盛り付け以外にも、パンやごはんなどの主食(ごはんは計量も)牛乳・ヨーグルト、味噌汁の準備など様々な準備が必要になります。簡単な朝食でもたくさんの数を準備するのはとても大変で、あっという間に時間が過ぎていきます。
その中でも特におかずの盛り付けが1番時間がかかります。そのため、どうしても朝食は簡単に盛り付けられることが前提になってしまいます。また、朝から数品調理し盛り付けるのはとても大変なため、1回で盛り付けられるものを1品という場合も少なくありません。
ですが、食事の回数は1日に3回。1週間で21回。朝食も1週間の食事の1/3を占めるとても大切な役割があります。食事には、栄養面を補給するだけでなく、食べる楽しみを持つこと、食事を美味しく食べることなどQOLを向上させる役割も含まれます。
そこで、おいしゅでは3品のおかずを調理・盛り付け済みにすることで朝食準備の時間を短縮できるだけでなく、昼食・夕食に劣らない食事を提供することができます。
刻み食もご用意していますので、別で刻み食を用意しなければいけないという手間もありません。また、使い捨て容器を使用することで、朝食後の洗浄の時間を短縮することができることもポイントです。
リニューアルした商品は3月以降に発売予定です★
ぜひ一度お試しください(*^▽^*)


試作時の試食写真です!同じメニューでも様々な調理方法や配合を試しています★
皆様こんにちは!はーと&はあと管理栄養士の篠原大之です。3月並みの気温が続き暖かさを感じますが、また一時的に寒気が流れ込むようです。寒暖差には十分お気をつけ下さい。
さて、今回は郷土料理についてお話いたします。郷土料理とは、その地の産物を土地柄に合わせて作られた料理のことです。先日、どうしてもお蕎麦が食べたくなり、以前から気になっていたお蕎麦屋に足を運びました。店主のこだわりが強いようで、入店に年齢制限があったり...メニューを見ると、そばがきセットという名前が!!「そばがき」?食べたことないし、管理栄養士として知らんわけにはいかんやろと思い注文!そばがきとは、蕎麦粉を使った料理で、麺としてではなく蕎麦粉を熱湯を加えて加熱し、かき混ぜて粘りを出して塊状にした食べ物のことです。ちなみに長野県の郷土料理です。箸で少しずつ取りながら醤油を付けて食べました。
はあとバランスのお食事にも、郷土料理が何品かあります。3月のメニューよりご紹介!
とり天:大分県の名物で、鶏肉を卵と水で溶いた小麦粉で作った天ぷら衣をまぶして油で揚げた料理。唐揚げよりさっぱりと食べられます。
筑前煮:家庭料理として全国的に知られていますが、もとは筑前国(現在の福岡県北西部)を中心とする九州北部のエリアで親しまれてきた料理。
いとこ煮:あずきと野菜の煮物です。材料を煮えにくいものから「おいおい」入れていくことから、「おいおい」を「甥甥」=いとこが語源の一つとされています。北陸地方、奈良県、山口県でよく食べられています。
是非一度お試しください!!
 こちらがそばがき!
こちらがそばがき!

どちらも風味良く美味しかったです!!
こんにちは!管理栄養士の松本千奈美です。
新型肺炎ウイルスが流行っていますね!!前回、風邪の予防についてお話しさせていただきましたが、同様に手洗い・うがい・アルコール消毒などで予防できるといわれていますのでしっかり行いましょう。また、バランスの良い食生活は予防の基本となりますので、しっかり食べてウイルスに負けない身体づくりを心がけましょう!
ちなみにの話10月号に手洗いの方法を載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。
さて、私は普段はあとバランスの開発を担当していますが、今回は新メニューが出来上がるまでの工程についてお話ししたいと思います。
★新メニュー完成までの工程★
①メニューの決定
最初は主菜・温菜・冷菜のどれを作るか決めるところから始まります。季節や既存メニューとの兼ね合い、年間の新商品開発数など、バランスを考慮して決めています。
②食材・商品の決定
次に使用する食材・商品を決めます。できるだけ季節感を取り入れるためにその季節に合った食材や、新しい話題の食品なども取り入れるようにしています。
③試作
使用する食材・商品が決まるとレシピを考えて試作に取り掛かります。試作ははーと&はあとのテストキッチンで1~2カ月繰り返して行います。
④新メニュー会議
試作が完成するとはーと&はあとの会議で試食します。試食後にアンケートを取り、一定の基準に達したもののレシピを工場に送ります。
⑤工場試作
送ったレシピをもとに実際に工場で試作します。工場で試作したものをはーと&はあとで再度試食し、合格したものだけが新メニューとして皆さんのもとに届けられます。
ざっと説明すると、このような流れではあとバランスの新メニューの開発を行っています。
この他にも食品会社の展示会や調理機器の勉強会などに参加して情報収集を行い、メニュー開発に活かしています。
でも実際にはいろいろな問題や失敗が多く発生します。その度にアイデアを出して試行錯誤を重ね、そうしてようやく完成となるのです★


試作の食材の仕込み・試作品の写真です(*^▽^*)