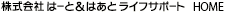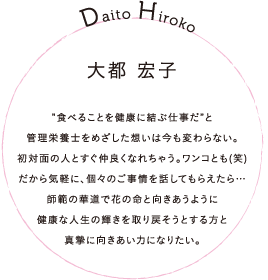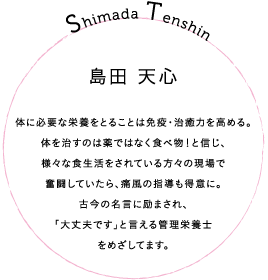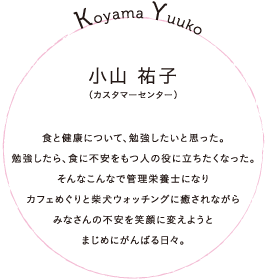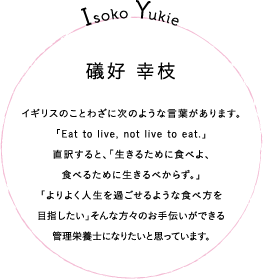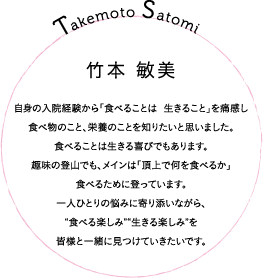こんにちは、管理栄養士の島田です。
師走となり、例年通り忙しい時期になってきました。
人流も増え、いい年越しに向けて皆さん活動的になってきたのを感じます。
さて、前回のブログでもご案内しましたが、現在長らくご利用いただいている方への訪問を行っています。
先日は、腎臓病の進行予防のため、長らく栄養コントロール食の塩分蛋白質調整食をご利用のH様、80代、女性で一人暮らしの方に訪問に伺いました。
最初はご主人と夫婦でご利用いただいていましたが、ご主人がご逝去された後は、H様のみ、お昼に栄養コントロール食をご利用いただいています。
当初はクレアチニンの数値は1.3、尿素窒素BUNが40と高かったことで、先生から減塩の指導を受けたのが利用のきっかけで、以降、定期的に腎臓内科で検査をされるたびに経過を確認していました。
今年になり、あまり量が食べられないし、数値も安定しているのでと相談があり。本人・ご近所にお住いのご家族への了解も得て、健康食に変更して引き続きご利用いただいています。
食事内容を変更してからも、数値等に変わりないか、通院のたびに配送さんからの声掛けで確認していました。
が、今回、久しぶりに訪問でこまかい数値まで確認すること出来ました。
クレアチニン0.88、尿素窒素13と、普通の方と変わりない数値でした。声も元気で、咀嚼嚥下にも問題なし、苦手な魚料理の時は少し残すこともあるようですが、好きな鶏肉料理は完食されていました。
介護サービスも受けておられますが、デイサービスなど人の集まるところは人間関係にストレスを感じると、自由に自宅で過ごされるのが好きなようです。自由なライフを支えられる食事サポートを長らく利用いただけていることに心より感謝できた訪問でした。
紅葉の季節、夜間拝観にいってきました。ライトアップされた竹林が素敵でした。
〈TaBeLu+倶楽部 デジタルカタログは下記をクリック〉
https://www810810.meclib.jp/heart810/book/index.html
<カタログをご希望の方は下記から閲覧・ダウンロードできます>
https://www.810810.co.jp/download/
はーと&はあと 管理栄養士 島田 天心