以前のブログで、「嚥下障害」と安全に食べる為の方法、「嚥下体操」を紹介しました。今回はそのpart2ということで、以前紹介しきれていない安全に食べる為の方法と、実際に私が利用者様と行っている「のど」の筋力訓練について紹介したいと思います。
軽く「のど」に手を当てて、だ液を飲み込んでみてください。ゴックンと飲み込む時に、「のど」が上に上がって下がるのがわかりますね(男性はのど仏の動きを見てもわかると思います)。この上下の動きがとても重要で、しっかり上に上がり切らない、タイミングがずれて上がる等動きが弱くなると、飲み込んだ物が「のど」に残ることや、気管に入ってむせることの原因になります。次に紹介する方法を試してみてください。
『安全に食べる(飲む)方法』
①声がゴロゴロするのは、だ液や食べた物が「のど」に残っているサインです。もう一回何も口に入れず、だ液を飲み込んでみてください(空嚥下)。それでも治らない時は、一度咳払いをしてからもう一度だ液を飲み込んでみてください。声が綺麗になりましたか?
②「のど」に毎回残った感じがするのは、一口の量が多すぎるからかもしれません。口にほおばらず、一回で飲み込める量を一口量にしてみてください。よくむせる人は、一口量をティースプン一杯(約5㎖)にしてみましょう。

 ③コップからゴクゴク飲むと顎が上がったままになっていて、ゴックンが追いつきません。一口量を口に入れたら、少し斜め下を見て飲み込んでください。「のど」がしっかり上がってうまく飲み込めるはずです。
③コップからゴクゴク飲むと顎が上がったままになっていて、ゴックンが追いつきません。一口量を口に入れたら、少し斜め下を見て飲み込んでください。「のど」がしっかり上がってうまく飲み込めるはずです。
「嚥下体操」は毎食前に行って欲しいですが、それに加えて、ゴックンに重要な「のど」の動きを鍛える筋力トレーニングを毎日の習慣にしましょう。「のど」にはたくさんの筋肉があり、弱くなった筋肉を鍛えることでゴックンが確実に行え、むせや飲み残しが減るはずです。
『おでこ体操』
 ①手を開いておでこに当てます。
①手を開いておでこに当てます。
②斜め下を見るようにして、おでこを下げ、手と押し合います。「のど」の辺りに力が入っているのがわかりますか?
③5秒押し合って5秒休憩、これを5回繰り返します。
食べること飲むことに少しでも気になることがあったら、はーと&はあとのスタッフに声を掛けてください。嚥下の専門の言語聴覚士(ST)田村がお一人お一人に合った方法を紹介できると思います。

 新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
2026年を迎え、地域における訪問看護の重要性は一層高まっています。65歳以上は29.3%に達し、在宅看取りを希望する方は43.8%と増加している一方、実際の在宅死亡率は17.4%に留まっています。この「希望と現実のギャップ」を埋めるために、私たちは地域の医療・介護の一端を担う事業所として、質の高いケアを提供できる人材の育成と定着にこれからも力を注いでまいります。
2025年の1月~11月に、ご逝去が理由で終了になった利用者は12名で、そのうち自宅で最期を迎えられた方は6名でした。在宅看取りを実現するためには、家族のマンパワー確保が欠かせません。配偶者だけでなく、お子さまもケアに関わり、家族全体で支えられたケースでは、大阪から福岡へ野球観戦に出かけたり、自宅ではメジャーリーグの試合観戦を楽しんだりと、残された時間が短い中でも穏やかな時間をご一緒することができました。こうした時間は、スタッフにとっても大きなやりがいとなり、ご本人やご家族が「有意義な時間だった」と感じてくださる姿は、看護師にとって大きな励みになります。
一方で、「施設に入るか」「自宅でみるか」など、今後の方針を迷いながら時間だけが過ぎ、ご本人の状態が悪化していく場合もあります。意思が定まらないまま支援を続ける状況では、看護師もまたジレンマを抱えることがあります。在宅か施設か、ご本人とご家族の本音が見えない場面では、支援の難しさを強く感じます。
その背景には、「ケアを点で終わらせず、継続的に支える」という私たちの信念があります。利用者と家族の想いを引き出し、最善につながる選択ができるよう、寄り添いながら意思決定支援を行っていくことが、訪問看護における大切な役割だと考えています。
 2025年10月より、管理者に加えてリーダー3人の体制を整えることができました。専門職としての見解を多職種連携に繋いでいくために、「記録の充実」と「連携方法とタイミング」を正しく判断していけるよう、リーダーと共に、人材育成に力を入れていきます。
2025年10月より、管理者に加えてリーダー3人の体制を整えることができました。専門職としての見解を多職種連携に繋いでいくために、「記録の充実」と「連携方法とタイミング」を正しく判断していけるよう、リーダーと共に、人材育成に力を入れていきます。
利用者が、「在宅チームの誰かに相談すれば、何とかなる」と感じていただけるように、今年も力を尽くしてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
朝晩の冷え込みがぐっと強くなってきましたね。
体調の変化が出やすい時期でもありますので、無理せずゆっくり過ごしましょう。
さて、今回は、食事のとき「ちょっと大変...」がある方へ向けた、簡単にできる工夫をご紹介させていただきます。
ご利用者さまのお宅へ伺う中で、
• 「ごはんをこぼしてしまう」
•「お箸がうまく使えない」
•「手が疲れてしまう」
•「座っている姿勢がしんどい」
といったお声をよく伺います。
実は食事動作は、指先だけでなく、体幹・肩・姿勢など、からだ全体の協調が必要な活動です。
だからこそ、「道具」や「座り方」を少し変えるだけで、驚くほど食べやすくなることがあります。
① まずは姿勢から整えましょう
食事中の姿勢が崩れると、腕が上がりにくくなったり、疲れやすくなってしまいます。
 ポイント
ポイント
• イスの高さは 足裏がしっかり床につく高さ に
• 膝と股関節は 90度くらい
• テーブルは みぞおちくらい の高さ
もし高さが合わない場合は...
• 座面にタオルやクッションを敷いて高さ調整
• 足が届かないときは 雑誌を数冊重ねて足台に
→ 姿勢が安定すると、手が自然と動かしやすくなり、疲れにくくなります。
② 食器と道具を工夫してみる
「持ちにくい」「すべってしまう」には食器の形が大きく関係します。
|
困りごと
|
おすすめの工夫
|
|
箸がすべる・握りにくい
|
滑り止め付き箸 / 太さのある箸
|
|
茶碗が持ち上げにくい
|
取っ手付きお椀 / 軽量茶碗
|
|
おかずを拾いにくい
|
内側にカーブのある深めのプレート
|
|
コップが持ちにくい
|
持ち手が大きいマグ / 滑り止めグリップ
|
 また、食器の下に滑り止めシートを敷くと、力が弱い方でも食器が安定して扱いやすくなります。
また、食器の下に滑り止めシートを敷くと、力が弱い方でも食器が安定して扱いやすくなります。
(滑り止めシートは100円ショップでも手に入りますよ)
③ 一口の量とペースを見直す
食べにくさを感じると、どうしても「早く食べなきゃ」と急ぎがちになります。
• ひとくちを小さく
•よく噛んで味わう
•途中でいったん深呼吸
この3つだけでも、
むせの予防・疲労軽減・満足感アップ につながります。
おわりに
 食事は 栄養をとるだけでなく、「楽しみ」でもある時間 です。
食事は 栄養をとるだけでなく、「楽しみ」でもある時間 です。
身体に合わせてちょっと整えてあげることで、
「食べやすい」「疲れにくい」「こぼれにくい」に近づけます。
「これ、私にもできるかな?」と感じるものがあれば、
訪問のときに遠慮なく声をかけてくださいね
![]()
 ③コップからゴクゴク飲むと顎が上がったままになっていて、ゴックンが追いつきません。一口量を口に入れたら、少し斜め下を見て飲み込んでください。「のど」がしっかり上がってうまく飲み込めるはずです。
③コップからゴクゴク飲むと顎が上がったままになっていて、ゴックンが追いつきません。一口量を口に入れたら、少し斜め下を見て飲み込んでください。「のど」がしっかり上がってうまく飲み込めるはずです。 ①手を開いておでこに当てます。
①手を開いておでこに当てます。
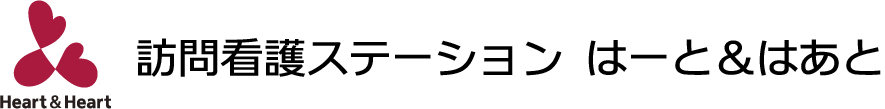

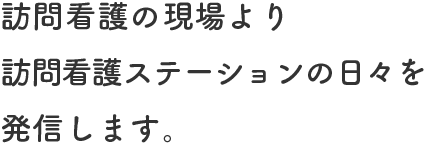




 新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。


