こんにちは。作業療法士の山﨑です。
訪問時には、必ず始めにバイタル(体温、血圧、脈拍、血中酸素濃度)測定を行っています。血中酸素濃度はパルスオキシメーターと言う測定器を指に挟んで測定するのですが、この時期は指先が冷たくて正確な数値が測れない方が多くいらっしゃいます。そういう時は、手指をマッサージしたり、温めたり、運動をしてもらい血流を良くしてから測るようにしています。
今回は、私が自主練習でよくお伝えする「手指の運動」をご紹介しようと思います。ちなにに画像は私の手です(^^ゞ
「手が冷たくて困っている」「指が動き難くい」「お箸が使い難くなってきた」「字が上手く書けない」等、手指に関するお悩みごとがある方は、ぜひ取り組んでみてください。
【手指の運動】
①グーパー運動
手をしっかり握って、大きく開きます。

②指折り動作
親指から順番に、一本ずつ指を曲げて行きます。曲げ終わったら、小指から順に伸ばしていきます。

※隣の指が一緒に付いてこないよう心掛けてください。
③ピンチ動作
親指の腹を人差し指の腹と合わせてつまみます。しっかりと伸ばして戻します。
親指と他4指それぞれ順番につまみ合わせていきます。

※この時、横からみた形がしっかりとOKサインのように〇になることが大切です。
④開く閉じる運動
掌が丸まらないように注意しながら、指を開いたり閉じたりします。

※指の間が均一に開くよう心掛けてください。テーブルに手を置いて行う方とやりやすいです。
手指を動かす事は、血流を良くする、巧緻性(手先の器用さ)の改善、また、脳を刺激し、認知機能を向上させることにも繋がるとされています。手指の運動はこれ以外にもたくさんありますが、まずはこの4つから始めて頂けたらと思います。運動の回数は、その方の状態にもよりますが、一度にたくさん取り組むよりも、小まめに取り組む方が効果的です。運動時は痛みに注意して、無理のない範囲で取り組んで下さいね。
 寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
寒さと共に空気も乾燥する季節となりました。肌は乾燥していませんか?あかぎれや引っ掻き傷はありませんか?
冬になり訪問する中で、利用者様の皮膚トラブルを目にすることが増えました。
そこで、自宅で簡単に出来るスキンケアについてご紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。
そもそも、なぜ冬は乾燥するのでしょうか?それは、気温が下がることで、空気中に含まれる水蒸気が水滴や氷に変わり、水分量が減るため空気が乾燥するそうです。また、暖房を付ける事でより部屋の乾燥が進みます。そうすると、肌からの水分が蒸発し、乾燥肌になります。
乾燥肌を予防・ケアするには
 ①刺激の少ないボディソープを使用する
①刺激の少ないボディソープを使用する
洗浄力の強いボディソープは必要な皮脂まで洗い流してしまう為、刺激の少ないボディソープで優しく洗体しましょう。
②シャワーや湯舟のお湯はぬるめにする
熱いお湯は肌にダメージを与え、乾燥肌の原因となります。38~40℃がお勧めです。
③ボディクリームやローションを使用する
お風呂上りは肌から水分が蒸発しやすく、放置すると肌が乾燥しやすくなります。水分が蒸発しないように、入浴後なるべく早くボディクリームやローションで保湿しましょう。
④部屋を加湿する
加湿器で部屋の乾燥を予防しましょう。加湿器がない場合は、濡れたタオルを干す、鍋でお湯を沸かす、水を入れたコップを置くなどして部屋を加湿しましょう。
また、乾燥肌によりあかぎれや引っ掻き傷が出来る事があると思います。さらにご高齢の方は四肢にスキンテアが生じているのをよく目にします。スキンテアとは摩擦やずれで皮膚が裂けたり、はがれたりする真皮深層までの皮膚損傷の事を言います。
傷が出来た時、どのように処置していますか?昔は赤チンやマキロンなどで消毒をして絆創膏を貼っていたと思います。しかし、現在消毒は行いません。消毒をする事により、雑菌を殺すだけでなく、傷表面の皮膚の形成を助ける細胞まで殺してしまい、その結果、傷の治りが悪くなると考えられているからです。まず、傷が出来たら洗浄しましょう。
傷の処置方法
①傷口を泡立てた石鹸でなでるように洗い、流水でよく流す
②出血している場合は、圧迫して止血する
③絆創膏を貼る(絆創膏でもよいですが、キズパワーパッド、うるおいパッド、クイックパッドなどがお勧めです)
スキンテアの場合は①~②まで施行後
③皮膚がめくれている場合は、皮膚を元の位置に戻す
④ワセリンなどを塗布しガーゼ(できればくっつかないガーゼ)で保護
⑤軽く包帯を巻いて固定する(包帯がない場合は肌に優しいテープやビニールテープでガーゼを止める)
※ガーゼをはがすときは、皮膚がめくれた方向と逆の方向からはがしてください!!


肌に優しいテープやくっつかないガーゼ、包帯はドラックストアや100円ショップに売っています。自宅にストックしておくと、いざという時に便利ですよ。
しっかり保湿して、乾燥肌を防ぎましょう。目指せ、ツルツル肌!!
不明点やお困りな事があれば、お気軽に訪問看護師にご相談ください。
 謹んで新年のお慶びを申し上げます。当ステーションでは、「自宅で過ごす利用者さんやご家族を最期まで支える存在でありたい」という思いで取り組んでおり、私が経験した在宅看取りのケースとその影響についてご紹介します。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。当ステーションでは、「自宅で過ごす利用者さんやご家族を最期まで支える存在でありたい」という思いで取り組んでおり、私が経験した在宅看取りのケースとその影響についてご紹介します。
2023年には12名の在宅看取りに関わらせていただきました。在宅看取りで初めて経験したことの一つは、"息を引き取る瞬間"に立ち会ったことです。
81歳男性、肺癌の方は緊急訪問した際に看護師の目を見て頷いた後、1分ほどで息を引き取られました。ほんの少し前まで会話が出来ていたお父様がお亡くなりになり、傍にいた2人の娘さん達は動揺していましたが、「ご本人が娘さん達を思って、看護師が来るのを待ってから最期の時を選ばれたと思う」とお伝えすると、「父の優しさなんですね」と受け止めていらっしゃいました。
51歳男性、膵臓癌の方の場合は、退室前に最後の確認をしようと思い状態を見ると徐々に呼吸の間隔が伸びていくので、退室せずに見守っていると息が止まりました。その時に、奥様から「一人の時じゃなくてよかった。一緒にいてくれて、傍にいてくれてありがとう」と、涙ながらにお言葉を頂きました。
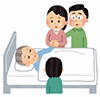 お看取りに対するご家族の強い不安がこの2人の共通点であり、最期の時に看護師が居合わせたことは偶然ではなく、ご本人がご家族のためを思って"最期の時を選ばれている"と思うこの感覚は、看取りの回数を重ねるごとに強くなっています。
お看取りに対するご家族の強い不安がこの2人の共通点であり、最期の時に看護師が居合わせたことは偶然ではなく、ご本人がご家族のためを思って"最期の時を選ばれている"と思うこの感覚は、看取りの回数を重ねるごとに強くなっています。
最期まで生ききる利用者さんに寄り添う経験が、自分自身の人生にも大きな影響を与えています。自分の命である時間について、誰と・どのように使うのかを真剣に考え、生きていく大切さを教えて頂いているように感じています。毎日顔を合わせることのできる家族や仲間と笑顔で温かなコミュニケーションを育むために、日々の小さな心遣いをもっと大事にしようと思います。利用者さんが身をもって教えて下さったことや、もっと生きたかったであろう想いを引継いで、自分の人生に落とし込むことが、利用者さんへの最大の恩返しではないかと思いながら、毎日を過ごしています。
 ターミナルの方と共に歩む貴重な時間を「辛い」だけで終わらせないように、スタッフには3つのことを身に付けてほしいと思っています。それは、①専門的知識を磨くこと、②知識が伝わるコニュニケーション能力を上げること、③ネガティブなこともありのまま受け止められる心の柔軟性(ネガティブケイパビリティ)です。
ターミナルの方と共に歩む貴重な時間を「辛い」だけで終わらせないように、スタッフには3つのことを身に付けてほしいと思っています。それは、①専門的知識を磨くこと、②知識が伝わるコニュニケーション能力を上げること、③ネガティブなこともありのまま受け止められる心の柔軟性(ネガティブケイパビリティ)です。
今年は在宅看取りを通して、自分自身を深く見つめながら全ての状況で柔軟に対応できる【優しくて強い人材】を育て、個々の人生についても語り合える職場にしたいと思っています。 2024年も精一杯、精進しますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。

はじめまして。事務員の河部実歩と申します。前職は情報サービス通信業の会社で営業事務をしていました。
出身は事務所があるここ、茨木市です。日常生活の中で、町を走るはーと&はあとの送迎車(デイサービス)をよく見かけていました。その時は「利用者様がたくさんいらっしゃるんだろうな」とただ思っていたのですが、新しく自身の環境を変えることになった際、はーと&はあとのホームページを見て訪問看護の存在を知りました。せっかくなら自分が生まれ育った町に何か少しでも貢献できればという思いがあり、事務職として訪問看護はーと&はあとで働かせて頂くことになりました。
まだ日は浅いですが、実際に仕事を進めていく中でスタッフの心の優しさに触れる瞬間がたくさんあり、スタッフ同士のコミュニケーションにも惹かれる面がありました。そのようなステーションの良さや温かさを、私は事務員として、間接的ではありますが利用者様に届けたいと思っております。
そして利用者様にはーと&はあとを選んでよかったと、心から言っていただけるような環境を作っていくことが、私の役目だと感じております。
医療・看護業界での勤務は初めてですが、利用者様に安心してサービスを受けていただくことができるよう、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。





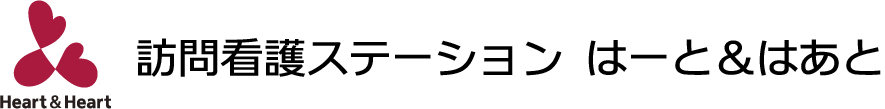

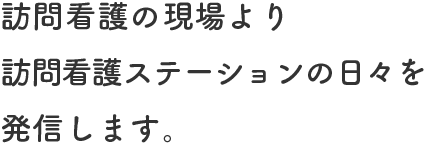




 謹んで新年のお慶びを申し上げます。当ステーションでは、「自宅で過ごす利用者さんやご家族を最期まで支える存在でありたい」という思いで取り組んでおり、私が経験した在宅看取りのケースとその影響についてご紹介します。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。当ステーションでは、「自宅で過ごす利用者さんやご家族を最期まで支える存在でありたい」という思いで取り組んでおり、私が経験した在宅看取りのケースとその影響についてご紹介します。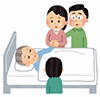 お看取りに対するご家族の強い不安がこの2人の共通点であり、最期の時に看護師が居合わせたことは
お看取りに対するご家族の強い不安がこの2人の共通点であり、最期の時に看護師が居合わせたことは ターミナルの方と共に歩む貴重な時間を「辛い」だけで終わらせないように、スタッフには3つのことを身に付けてほしいと思っています。それは、①専門的知識を磨くこと、②知識が伝わるコニュニケーション能力を上げること、③ネガティブなこともありのまま受け止められる心の柔軟性(ネガティブケイパビリティ)です。
ターミナルの方と共に歩む貴重な時間を「辛い」だけで終わらせないように、スタッフには3つのことを身に付けてほしいと思っています。それは、①専門的知識を磨くこと、②知識が伝わるコニュニケーション能力を上げること、③ネガティブなこともありのまま受け止められる心の柔軟性(ネガティブケイパビリティ)です。