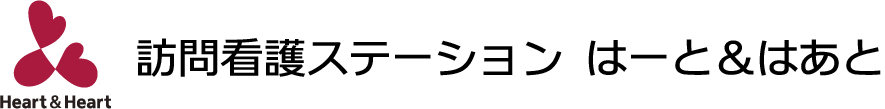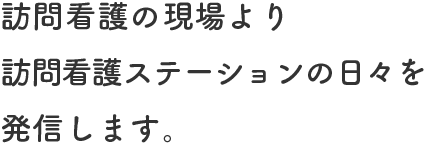初めまして。看護師の山岸綾子と申します。
私はこれまで、消化器外科・内科、救急などで勤めてきました。
私には忘れられない患者さんがいます。半身麻痺があり、サポートを入れてひとり暮らしをされていた方が入院してきました。再梗塞の為、全麻痺、嚥下障害、失語症を認めており、体調があまり良くはなく、ご本人は「自宅へ帰りたい」と強く希望してるものの自宅への退院は困難で施設への転院となりそうでした。
そんな時、自宅退院を受け入れる訪問看護が見つかり、無事に自宅へ帰ることが出来たのです。10日ほどでお亡くなりになりましたが、その10日間は好きなものを食べて、飲んで、過ごされたそうです。サポートがあった事で住み慣れた自宅に帰る事ができ、ご自身らしく過ごすことができたと強く実感した症例でした。
以前から、入院した時の「点」だけのその人をみるのではなく、その人の人生の一部に寄り添える訪問看護に関心があり、この事をきっかけにより訪問看護師として働きたいと思うようになりました。住まれた自宅で季節を感じながら、その人らしく、安心して過ごせるようにサポートさせて頂きたく思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。
こんにちは!看護師の播磨です。
秋があっという間に去り、冬が訪れましたね。
私は寒いのが苦手ですが、ぽかぽかの日差しはとても好きです。
さて、今回は寒さにちなんだ気を付けてほしい事への呼びかけをしていこうと
思います。
この時期になるとニュースでもよくヒートショックの話題を耳にします。
まず、寒くなると「冷え」から身体が熱を逃さないよう全身の血管が収縮します。血管が収縮すると血圧は上がります。
これから室内では暖房機器を使用する事が増えると思います。室内を温める事で身体の「冷え」もなくなり、ほっと一息つくころには身体もぬくもり寒さで収縮していた血管も緩みます。これを拡張といい、血圧も下がります。
この寒暖差が急なほど血圧変動につながり、眩暈やふらつき、最悪心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わることもあります。
この症状が出やすい場面の一つが「入浴」です。寒くなるとどうしてもお風呂に浸かりたくなりますよね。
ヒートショックを招かないようには⇩
*脱衣所を暖房器具にて温めて寒暖差の少ない環境を整える
*すぐに浴槽へ入らずシャワーで身体をぬくめてから浸かる
*湯温は41℃以下 10分目安で浸かる
*浴槽からの立ち上がりはゆっくりと。
上記に注意しながら、みなさん安心してほっと一息つける入浴ができますように。
寒さに負けずに皆様が元気に過ごせることを願っています。
作業療法士の古杉です。
はーと&はあとで働き始めて半年が経ちました。
半年前は初めての訪問リハビリという事もあり不安でいっぱいでしたが、今は訪問を回っている時間がとても楽しいです。
「リハビリに来てくれるから元気になった」
「リハビリの時間が楽しい・あっという間」
「来るの待ってたよ」等
この他にもたくさん嬉しい言葉を言って頂けることがあります。
また、利用者様からご様子・変化・お困りごと等聞かせて頂いており、困っている事に対しリハビリを行っていき、出来るようになってきた時に「これができるようになったよ」と喜ばれて報告をお聞きすることがあります。
例えば、リハビリを始めた時は家の中での歩行・動作も転倒リスクが高かった利用者さんがいました。リハビリをしていき屋外歩行が出来るようになると、ご本人も介入時より動けるようになっていることが実感できて、「こんなに動けるようになれて嬉しい」「来てくれるおかげ」と大変喜んで下さりました。
利用者の方々の笑顔や嬉しいお言葉が励みになって毎日楽しくお仕事出来ています。これからも利用者の方々の力になり楽しくお仕事出来るよう過ごせていけたらと思います。
訪問看護ステーションはーと&はあとの管理者・山本です。
この度、利用者170名で6周年を迎えられたのは、一重に利用者様・医師・ケアマネジャーなどの皆様のおかげであり、心から感謝申し上げます。これからも、"困った時に一番に思い浮かべてもらえる事業所" "困った時に最後の砦としての役割が果たせる" そんな事業所になるべく、努力をしていきます。
私達の仕事をレストランに例えると、"どんなに接客がよくても、料理が美味しくないとリピートはない" "逆にどんなに料理が美味しくても、接客が悪いとよさが広がっていかない"と思っています。私たちにとって、料理にあたるのがケアで、接客にあたるのが連携だと思っています。
ケアと連携の質の向上のために、管理者とリーダーを中心にOJTを実施しています。ケアが根拠に基づいて実施できているか、内容に過不足がなかったか。連携においては、報告の必要性を見極められているか、報告時は状況に応じて、電話・FAX・メールの選択が適切にできているかを、指導しています。どのスタッフが担当をしても、同じ質で「ケアと連携」が提供できるよう、サービスの均一化を目的としています。
思っているだけでは現実は動かず、行動が伴って始めて、そこに込めた思いが輝き出すということを、スタッフ一人一人が体感していくような7年目にしていきたいです。共に働くスタッフの成長なくして、事業所の成長はありません。地域を支える訪問看護を目指して、行動していきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 6周年を記念して、その日に事務所へ集まることができるスタッフ11名と撮影しました。他7名が在籍しています。
6周年を記念して、その日に事務所へ集まることができるスタッフ11名と撮影しました。他7名が在籍しています。
訪問する時や事務所で密になる時はマスクを着用しています。