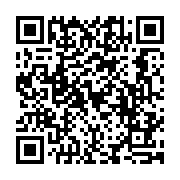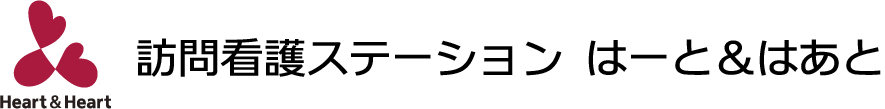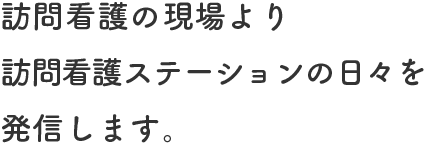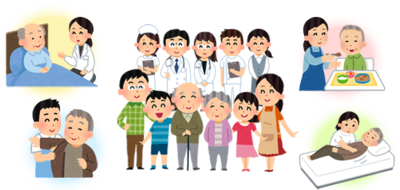はじめまして。理学療法士の杉野美香と申します。はーと&はあとで2022年10月より働かせていただくことになりました。
私はこれまで急性期~慢性期、病院勤務における外来リハビリテーション、整形外科のクリニックや訪問診療からの訪問リハビリ、訪問看護のリハビリテーションに携わってきました。経験年数は16年になります。その経験で大切にしている事は、利用者様やそのご家族、周りに関わる多種職の皆さんとのコミュニケーションです。
在宅ではより利用者様との距離を縮めて関わることになります。住み慣れたご自宅でのお困りごとや生活での過ごしづらさを感じておられること、お体のこと、またそれのみならず今までお一人お一人が経験されてきたお仕事のお話、ご趣味、関心ごとなど。何でも構いません。少しずつでいいので利用者様ご自身のことを教えていただきたいです。そういった全ての対話がリハビリに結びついたり、たとえ結びつかなくても話す事で笑顔になっていただければ、それもふくめてリハビリテーションだと思っております。
利用者様から学んだことを成長の糧にし、理学療法士という肩書の前に、より安心して気持ちに寄り添える人間として、少しでもお役に立ちたいと考えています。私自身、大阪生まれの大阪育ち。子供は2人。趣味はフラダンス、ドラマや映画鑑賞、食べることです。新たにはーと&はあとの一員として精進して参りますのでよろしくお願い致します。
この度、『訪問看護はーと&はあと』は2022年10月1日で5周年を迎えることができました。ひとえに皆様のお力添えのおかげと感謝しております。利用者が地域で安心して生活できるように「在宅療養を支える存在であること」、「自宅にいながら、病院のような安心感を提供できること」、それらが訪問看護に課せられた使命であり、大きな役割だと感じています。
その役割を果たしていくために大事にしてきたことが2つあります。一つ目は、「利用者に寄り添った質の高いケアが提供できること」です。個々の利用者に合わせた柔軟なケアができること、医師の指示に基づいた適切なケアができることを柱に、スタッフ教育をしています。様々な問題が起こるたびに、スタッフ個々に話を聞いて事例の振り返りをし、同じ問題が起こらないように改善策を考えるとともに、全体カンファレンスでも事例検討をし、個々の学びを全体でも共有するようにしています。
二つ目は「迅速で的確な報告をすること」です。訪問看護が地域に根差した存在であるためには、"連携"が欠かせないと思っています。『迅速』については、問題発生時に、如何に早く情報共有ができるかによって、利用者支援に繋がるまでの時間が変わってくるため、重きをおいて行動しています。報告がしやすい体制作りとして、自宅からFAXが出来るようにしたり、日々の訪問記録をそのまま報告に使用できるように様式の改訂を重ねたことが、迅速な報告に繋がっていると思います。『的確』については、「内容が端的」で「連絡手段が適切」であることを重視しています。情報共有においては、非同期であるFAXを第一選択としています。その理由は、相手の業務を中断させることなく、かつ文字として残る形での連携ができるからです。ただし、非同期での連携を軌道に乗せるためには、顔の見える関係作りや、電話によるフォローが必要だとも感じています。また情報共有とは別に、緊急時の指示確認や、相談が必要な場合には電話を用いて、その場で問題が解決するようにしています。必要性に応じて、電話も使いながらスムーズな連携をしていきたいと思っています。
5周年を迎えた今、利用者が150名を超え「はーとさん、お願い」と先生やケアマネジャーから、お声をかけて頂けることが増え、とても有難く感じるとともに身が引き締まる思いです。これからも、地域から必要とされる事業所であり続けるよう邁進いたしますので、変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い致します。
夏休み・お盆休みもあっという間に終わりましたが、皆様いかがお過ごしですか?
我が家の夏休みは、娘の希望で、私のおばあちゃんが暮らす老人ホームへ会いに行きました。娘にとってはひいおばあちゃんです。コロナ禍ということもあり、面会は中には入らずに窓越しで、電話をつなげて話しました。
今年4歳になる娘は、ひいおばあちゃんに喜んでもらいたくて、園で習いたてのお歌をたくさん歌ってあげていました。30分の短い面会時間でしたが、一生懸命に歌うひ孫の姿をみて、ひいおばあちゃんは笑顔で手拍子をしながら、時より涙を流して喜んでくれていました。
娘の記憶に残る良い思い出になるといいなと思い、写真に残しました。その時の写真がこれです。

ところで、皆さんは、子どもの頃の夏休み、何をして過ごしましたか?『夏休み』ときいて、何が思い出されますか?
私は、手に汗をかきながら切符を握りしめ、一人で宮城県の祖父母の家に行き、夜は祖母と手をつないで寝たあたたかい思い出や、友人と川遊びをして、みんなで協力して魚を素手で捕まえた思い出など、たくさんの楽しい記憶が思い出されます。
ちなみに、こんな風に自分の過去のことを話すことは、精神を安定させる効果があると言われており、これを回想法といいます。
(回想法とは、長寿科学振興財団によると「自分の過去のことを話すことで精神を安定させ、認知機能の改善も期待できる心理療法のこと」と定義されています。)
回想法で重要なのは、『思い出す』だけでなく、思い出したことを聞き手に『語る』ということだそうです。人に話すという行為は、脳に大きな刺激を与え、認知症の症状の緩和や進行の抑制に効果があるとされています。
ご家庭で回想法を実施する時に特別なものは必要ありません。ご自身やご本人が若い時に使っていた物や写真などを用意して、その思い出話を話す、もしくは耳を傾ける。それだけで、話し手の脳に刺激を十分に与えることができると言われています。
何よりも回想法で期待される大きな効果は、『心を落ち着かせることができる』ということがあります。
夏休み、孫やひ孫の面倒で疲れたわ~。毎日暑くて体がしんどいわ~。そんな時は、回想法をお試しください!もしよろければ私が訪問した時に思い出話をお聞かせ下さい。心を落ち着かせる、そんなお手伝いができたら嬉しいです。
この度、訪問看護ステーションはーと&はあとのLINE公式アカウントを開設しました。
訪問看護の利用を考えているご本人様・ご家族様、ケアマネジャー、医療関係者など、LINE公式アカウントより、気軽に相談が可能です。
また、当ステーションのお仕事に興味がある看護師・セラピストからの問い合わせも、お受け致します。遠慮なく求人についてご質問下さい。
尚、公式アカウントに友だち追加をしても、アカウントページ上から第三者に友だち情報が公開されることはありません。ご安心下さい。
下記の「お友だち追加」ボタンを押すか、「QRコード」を読み込み、LINEアプリを開いて友達追加をお願い致します。トークルームよりご相談をお待ちしております。
![]()