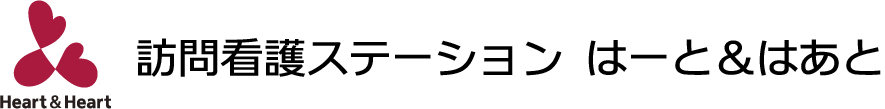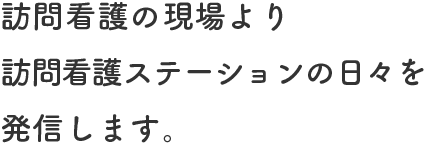はじめまして。看護師の入澤いずみと申します。私はこれまでに腎・泌尿器科病棟と精神科単科の病院に勤めてきました。看護学生の時に初めて訪問看護という分野を知り、病院ではなく個人が生活する場で看護ケアをできるということに感銘を受け、いずれ訪問看護に携わりたいと考えていました。
以前働いていた病棟は、長く精神科で療養され加齢と共に身体的なケアが必要になった方、また身体的治療が必要とされるが精神疾患があるために身体科の入院が適応されない方などが多く療養されており、内科的なカラーの強い病棟でした。そして長く療養されそのままお看取りになる方もたくさんいらっしゃいました。
可能な限り安らいだ気持ちをもって過ごしてほしいと思いケアにあたりましたが、病棟ではどうしても業務の流れが優先されることが多く歯がゆく感じることもありました。人それぞれの希望やペースに沿った看護を提供したいと考え、利用者様の最期までケアすることに力を入れているはーと&はあとに転職しました。
訪問看護は初めてですが、日々の生活で不安に思うことや大事にしていること等、お話をよく聞かせていただいて、利用者様・ご家族様の生活様式に沿ったケアを提供し安心してご自宅で過ごせるお手伝いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
厳しい暑さが続いておりますが、皆様どうお過ごしでしょうか。熱中症に注意をしながらも、まだマスクの外せない生活が続いています。今日はそのマスクの下、お口の中についてお話したいと思います。
口の中を綺麗に保つことは、全身の健康状態の維持と向上を目指すケアであると、世界では言われています。
口の健康は全身の健康に影響しており、歯周病菌は脳梗塞や動脈硬化、心筋梗塞、誤嚥性肺炎などの病気にかかるリスクがわかっています!
その為、口腔内を清潔に保つことが、とても重要になります。
口腔ケアの必要性
①口には食べ物カスが残りやすく、温度や湿度が口腔内の細菌にとって住みやすい環境である為、細菌が繁殖しやすい。
②口腔内を清潔に保つ自浄作用のある唾液も、高齢者になると唾液の分泌量が減ってしまう。またマスク着用により、口呼吸となりやすく乾燥しやすい。
口腔ケアを行う目的
●口腔内を清潔に保つ
歯周病を始めとする細菌による病気を防ぐことや、口臭の改善にも繋がります。
●口腔機能の維持・向上
口腔ケアをすることで、話す、食べるなどの口の働きや舌の機能を維持・向上させることができます。生活の中の楽しみの一つである食事の楽しみを増幅させてくれることで、QOLの向上にも繋がります。
●誤嚥性肺炎などの感染予防
口腔ケアをすることは、口の中の細菌が減るため、細菌を含む唾液や食べ物が誤嚥され、肺などに細菌が侵入することで発症する誤嚥性肺炎を防ぐことができます。この誤嚥性肺炎による死亡者数は近年、増加傾向にあります。
●味覚の改善
口腔ケアを行うことで舌の汚れを綺麗に取り除くことで、味を感じやすくなります。味覚の改善は食欲不振や低栄養状態の予防に繋がります。
●認知症を予防する
口を開けたり閉じたりして噛んで食べるという行為は、脳に酸素を送ったり刺激を与えたりするため、中枢神経を活性化し認知症を予防するとされています。歯が20本以上残っている人に比べて、歯がなく入れ歯も使っていない人は、認知症になるリスクが1.9倍も高いと言われています。
口腔ケア用品について



高齢者の方や、自分ではケアが難しい方も多くいらっしゃると思います。お口の中はデリケートな部分でもあるため、他人に見せることに抵抗を感じられるとも思います。しかし、上記でお話したように、口腔ケアを行うことで多くのメリットがあります!最近では、訪問してくれる歯医者さんも増えてきました。
お口にお悩みがあれば、いつでも訪問看護師にお気軽にお声掛けください。
こんにちは。作業療法士の山﨑です。
作業療法士は、身体機能改善に伴う運動の他に、自助具を用いて日常生活をサポートすることがあります。今回は、その自助具についてご紹介したいと思います。
自助具とは、麻痺・筋力低下・関節可動域の制限等で日常生活動作(食事・整容・入浴等)が困難になった方の為に、自分で行えるよう作成された道具です。
自助具は、介護用品ショップやインターネットからも購入可能ですが、自分に合ったものを使用しないと使い辛く、逆に体の負担になる恐れもあります。そこで、作業療法士が一人一人の心身機能に合わせ、生活環境なども考慮して選定する事が大切になっていきます。また、市販されているものでは合わない場合、その方に合わせて改良や一から作成も行います。
例えば、スプーンやフォークが握り難く食事ができない場合には、太柄スプーン、くるくるグリップ、カフ等があります。色々な種類の中から、どれが一番使いやすいか選択し、動作の練習を行っていきます。


私が作成したことのある自助具として、長柄付ブラシがあります。股関節の手術後の方で、足元に手が届かず、足の裏が洗い難いとの訴えがありました。そこで、楽な姿勢で足の裏を洗うことができるように、ブラシに長い柄を取り付けた自助具を作成しました。
「これで一人でお風呂に入れる」と喜んでおられました。
自助具以外でも、ペットボトルのストロー付きキャップが役にたった方がおられました。夜中に「喉が渇いた」と起こされて困っていると、奥様からご相談がありました。そこで、100円ショップにあるペットボトルのストロー付きキャップを提案しました。
次に伺った時には、枕元にペットボトルを置いて自分で飲めたので、夜中に起こされることもなくなったと喜んでおられました。
このように、福祉用具や自助具ではないものでも、介護の現場で役に立つものがあります。悩んでいる事はどんな些細なことでも、何か解決できる方法があるかもしれないので、ご相談して頂けたらと思います。利用者様の機能改善だけではなく、ご家族様の介助量の軽減も大切だと考えています。
最後に、私はよく100円ショップに「何か良いものないかな~。」とフラッと立ち寄ることがあります。最近では介護用品も増えてきており、自助具に使えそうな物がないか探しています。いきなり介護用品ショップで購入するのに抵抗がある場合には、手ごろな価格で試してみやすいかもしれませんね。
はじめまして。作業療法士の川部泉と申します。5月からはーと&はあとで働くことになりました。地元は茨木市です。結婚してすぐに夫の転勤で愛知県・千葉県に住んでいましたが、3年ほど前に大阪へ戻ってきました。地元で育児ができること、仕事ができることをとても嬉しく感じています。
今まで精神科の病院、療養病棟、デイケア、デイサービスと様々な場所で勤務してきました。千葉県ではヤクルトレディをしていたこともあります。訪問リハビリの仕事は初めてですが、他職種の方とも連携をとりながら、丁寧な仕事を心がけていきたいです。
どんなことを大切にしているのか、どんな生活を望んでいるのかなど、ご本人やご家族様とコミュニケーションをとらせていただきながら、お一人お一人に合わせたリハビリや、自宅で安心安全に暮らせるような環境作りのお手伝いをさせていただけたらと思います。「川部さんにだったら話しやすいわぁ」「川部さんと会えば元気になるわぁ」と感じていただける存在になりたいなと思っています。
今までの経験を活かしながら、でもブランクもあるため、また一からの気持ちで勉強もしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。