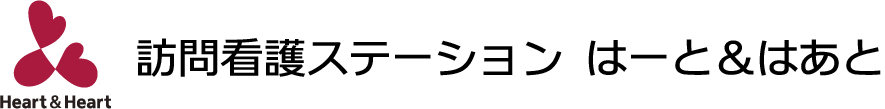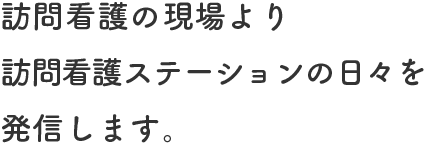初めまして、作業療法士の山﨑友絵と申します。私はこれまで急性期の病院で勤務し、その間訪問リハビリも経験しました。結婚を機に大阪へと引っ越し、2021年3月よりはーと&はあとの訪問看護で働かせて頂くことになりました。
病院では、脳血管疾患による麻痺や高次脳機能障害、人工股関節置換術後や手の外科疾患等の整形疾患、廃用症候群やがん疾患の患者様に対するリハビリテーションに携わっていました。何気ない会話の中で出てくる本当の気持ちを大切にしたいと関わらせて頂いていました。例えば、「無理だと思うけど、大したことではないけれど・・」という言葉の裏には「本当はこんなことがしたい、ちょっと困っている」という思いがあるのです。福祉用具等の利用や工夫をする事で、楽になったり、安全になったりする事もあります。
訪問リハビリでは運動や日常生活の動作訓練の他にも、住み慣れたご自宅で安全に、より安心して過ごせる環境作りを提案させて頂けたらと思います。どんな些細なことでも相談して頂け、利用者様やご家族様のご希望添えるリハビリテーションの提供と柔軟な対応ができるよう努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
初めまして理学療法士の松元裕作と申します。私は生まれも育ちも沖縄県で、妻の出産を機に妻の故郷である関西に引っ越して参りました。関西に住むことはもちろん関西で働くことも初めてで、只今いろんな事を勉強中です。またコロナ禍に、この職場に出会えたことに感謝しています。暖かい土地から来たため冬はちょっと苦手ですが、空気の透き通るような冷たい空気に凛とした気持ちになります。
沖縄県にいた時は長年デイケアで勤め、高齢者と接する機会が多く、利用者様の中には転倒や病状の悪化で入退院を繰り返し、施設へ入所される方もいらっしゃいました。利用者様は長年住み慣れた家で、過ごしたいという方がほとんどで、支えておられるご家族も、仕事や予定がある中、生活と介護負担で疲労があるのも現実です。
利用者様、ご家族様のご希望に沿いながらご自宅で過ごせるようにサポートを行っていく訪問看護に魅力を感じました。これまでの経験を活かして、最善のサービスを提供できるよう努めて参りたいと思います。スタッフの皆さんと力を合わせながら、私自身もこの会社の一員として精進したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
初めまして看護師の徳井歌慧です。私はこれまで病院の血液内科・神経内科・小児科・眼科、保育園で勤務してきました。
私が小学生の頃、同居する祖母がパーキンソン病と認知症を発症し、母が自宅で介護をしていました。当時は介護保険制度が出来たばかりで、制度がよく分からない中、親身に話を聞き、手を差し伸べてくれたのがケアマネジャーと看護師でした。私はその助けを目の当たりにし、看護師の道を目指しました。母も長い期間ほぼ一人で介護を頑張っていたため、この時本当に助けて頂いたと胸を撫でおろしていました。
今までの看護経験を活かし、次は訪問看護師として 「私の母と同じようにご自宅で頑張っていらっしゃる家族や利用者様のお力になりたい」 という思いで、新たに出発します。利用者様とご家族が、いつも笑顔で安心して過ごせるように、一番近くで寄り添いサポートできるよう頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
旧年中は一方ならぬご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。
2020年を振り返り、最初に思うことはやはり、コロナ禍で日常が様変わりしたことではないでしょうか。当ステーションは、緊急事態宣言が出された4月より、可能なスタッフは自宅から利用者宅へ直行直帰とし、朝礼・終礼はビデオ通話での参加としました。変更した当初は、スタッフと直接顔を合わせる機会が減る中で、スタッフの状態や訪問の様子を把握することに不安を感じましたが、スマホやタブレット、クラウド型の電子カルテなどを活かし、現在は円滑に情報共有ができています。今後も感染予防対策など、気を付けることは多くありますが、訪問看護が今まで通り出来ていることに感謝しています。
私自身は管理者として3年目を迎えました。管理者になった当初は4人だったスタッフが、現在では常勤・非常勤の訪問スタッフ、事務員を合わせて14人になり、利用者も116名となりました。利用者や関係機関の期待に応えるべく、はーと&はあとの組織力向上に力を注いでおります。
スタッフとは6月と12月の年2回、個別面談をしています。昨年の6月の面談では、「山本の風当たりが強すぎる」という意見が、一部のスタッフから出ました。話しやすい雰囲気は作っているつもりですが、何度も同じミスを繰り返すスタッフに対し苛立ちが表に出ていたのかもしれません。はーと&はあとで働くスタッフの為、ひいては利用者の為にしていることが機能していないと感じ、一人になると涙がこぼれたこともありました。しかし、それからは今まで以上にスタッフとの意志の疎通を意識し、相手の立場に立った伝え方を心がけています。また、全てのスタッフに何事も出来ることを求めるのではなく、得意な技術を持った者が、それを苦手とする者を補完し合う組織でありたいと思っています。
今年の私の目標は、「管理者として自分自身が成長すること」です。そのために必要なこと、やっていきたいと思うことは、"とにかく行動"に移したいと思っています。ある訪問看護の管理者が「神は細部に宿る」という言葉を大事にしていると聞き、私もそれ以来、その言葉を大切にしています。この意味は、"細かい部分までこだわり抜くことで全体としての完成度が高まる"というもので、細かい部分までこだわって行動したいと思っています。私は昨年テレビドラマで放送されていた、半沢直樹という人物が大好きです。半沢直樹のように仕事に熱く、組織を引っ張り、利用者の為になることを精一杯、努力していきたいと思います。今年もどうぞ宜しくお願い致します。